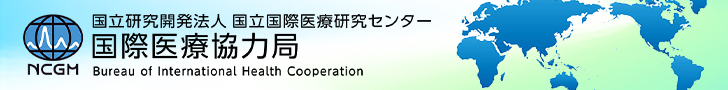2024
12/09
国際保健の専門家として25年の海外経験を持つ薬剤師
-
国際医療
-
海外
~学び続けることが好きな人に向いている仕事~
海外で活躍する医療者たち(43)
保健医療分野のコンサルタントとして海外活動に従事
――金森さんの海外での活動は、通算すると25年になるそうですね。
金森 はい。青年海外協力隊が最初の海外活動でした。大学では薬学を専攻していましたが、世界を舞台に働くことに魅力を感じ、国連での仕事や国際保健に興味を持つようになりました。でも国連の仕事をするには経験もいるし、語学もできなければならない。留学するといってもお金が必要です。そこで、まずは経験を積みたいと思って青年海外協力隊に参加し、ザンビアの大学で薬学の講義を担当しました。
その後、ハーバード大学で国際保健の修士を取得し、国連薬物統制計画(UNDCP)にアソシエート・エキスパートとして参加して、タイとオーストリアで違法薬物の予防や治療のための活動に従事しました。戻ってからは、ODAを専門とする民間のコンサルティング会社に勤務し、保健医療分野のコンサルタントとしていろいろな国で技術協力の仕事をしながら、東京大学で国際保健の博士を取得しました。
――コンサルタント会社では、どのような国で、どんな活動をしたのですか。
金森 勤務していた22年の間に、タンザニア、スリランカ、セネガル、フィリピンといった国に赴任しました。
タンザニアでは、マラリア患者の診断や看護ケアの能力向上のための研修プログラムを作成する業務に従事しました。スリランカでは、保健省の各部署の計画立案能力を向上させる仕事、またセネガルでは、州や県の保健局の年次計画立案能力を向上させる仕事をしました。スリランカとセネガルでは、病院や保健センターに日本の5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)も導入しました。
フィリピンは一番長く、約9年間赴任しました。前半は妊産婦ケアの向上のための政策・施策作りへの提言、後半は覚せい剤依存症患者のための治療プログラムを作って全国に広める仕事でした。
私は薬剤師ではありますが、これまでに国際保健の中でも異なる分野のプロジェクトに携わってきましたので、これといった専門分野がないというのが正直なところですね。

タンザニアの地方の保健センターにて、マラリア顕微鏡診断の巡回指導に参加している様子
――途上国の薬剤師も、日本と同じような仕事をしているのでしょうか。
金森 日本の薬剤師と同様の仕事はありますが、服薬指導はあまり重要視されておらず、単にビジネスとして薬を売る人が多いようです。薬剤師という資格制度はあると思いますが、私が滞在した30年ほど前のザンビアでは、薬剤師が養成できていないのか海外の薬剤師が多かったです。今は状況も変わっているだろうと思いますが、国際保健の現場で薬剤師に出会うことはあまりないので、少ないのかもしれません。
フィリピンでの薬物依存症治療プログラム
――では、フィリピンの薬物依存症治療プログラム導入プロジェクトについて少し詳しく紹介してください。当時のフィリピンでは、薬物依存症の治療はどのように行われていたのでしょうか。
金森 フィリピンは薬物依存症の人がかなり多いため、治療プログラムも提供されています。ただ伝統的に行われているそのプログラムは、規則正しい生活をさせるなど、軍隊的で科学的根拠に乏しい方法でした。
――プロジェクトで新たに導入したプログラムとはどのようなものなのですか。またどのようにして広めたのでしょうか。
金森 元々アメリカで開発されたマトリックスモデルというプログラムで、認知行動療法を用いて治療するものです。それぞれの患者さんが、自分はどういう状況だと薬物を使いたくなるのか、例えば金曜日の夜、お金を持っている時、バーに行った時など自分自身で学習し、グループセッションを何度も繰り返しながら行動を変えていきます。
この治療プログラムを、まず一つの施設に導入して機能することを確認し、徐々に他の施設の臨床心理士の方にも研修を受けていただいて広めていきました。
――伝統的に行われている方法がある中で、新たなプログラムという提案は受け入れられたのでしょうか。
金森 新たに導入する治療プログラムは、国の第一人者といえる方々と一緒に作っていきましたが、軍隊のような生活スタイルを維持したまま、認知行動療法を入れていくことになるので、最初は皆さんとても懐疑的でした。「絶対にうまくいかないだろう」といわれていました。でも時間をかけて説明したり、ワークブックを作って見せたりしていくと、空気が変わっていって協力いただけるようになりました。
現在このプログラムは、フィリピンにある全ての入院治療施設と外来治療施設に導入されています。
――日本でも、薬物依存症の治療は行われていますか。
金森 世界的に見ると日本は薬物依存症の方が少ない国ですが、治療プログラムを提供している施設はあります。刑務所でも、また出所後の人に対しても治療は行われています。薬物はいろいろありますが、覚せい剤という点では日本とフィリピンは共通です。

フィリピンでの薬物依存症治療プログラム導入プロジェクトのセミナーでプレゼンテーションを行っているところ
家族で赴任先へ、各国での生活は
――海外での生活が長いと、私生活でもいろいろな経験をされているのではないかと思います。
金森 そうですね。1994年に参加した海外協力隊で派遣されたザンビアでは、ひどい生活をしていました。それまで料理などしたこともなかった上に、講義の準備で毎日忙しかったため、ろくなものを食べずにいたらガリガリにやせ細ってしまいました。栄養状態が悪かったこともあり、マラリアに3回もかかりました。その一方で、幼少期からバイオリンを習っていたので、ザンビアにもバイオリンを持っていっており、地元のオーケストラでコンサートマスターをしていました。
2008年から赴任したスリランカでは2009年に内戦が終わったのですが、終戦の直前にコロンボが北部タミル軍の空襲に遭い、町全体が停電の中を不安な気持ちで過ごすという経験をしました。バイオリンの方は、地元のオーケストラに2つ掛け持ちで参加していました。週2回、4時間ぐらい練習があり、ほぼ毎日練習しているような感覚で忙しかったです。
フィリピンでは日本人駐在員で結成される音楽バンドに入り、ショッピングモールなどで頻繁にライブをやっていました。私はボーカルとバイオリン担当で、それまでとは違う路線でエレキバイオリンも弾いていました。
――赴任先にはご家族も一緒に行ったのですか。
金森 はい、そうです。アパートを借りて家族で暮らしていました。20年ぐらい連続で海外にいたことになるので、2人の子どもはほぼ海外の学校で育ち、フィリピンのインターナショナルスクールで高校を卒業しました。
アフリカではお手伝いさんを雇っていましたが、お金を騙し取られるという経験をしたこともあり、フィリピンではお手伝いさんはやめました。フィリピン料理の印象はほとんどなく、食事は主に家で和食を食べていましたし、外食もフィリピン以外の料理ばかりでした。
――フィリピンの駐在期間中にはコロナ禍もあったと思います。
金森 そうですね。ロックダウンになってしまうと、薬物依存症の治療施設の患者さんは全員退院させられました。退院させられた人たちの状態は心配でしたが、とても治療を受けられる状況ではありませんでしたね。
私たち駐在員も、JICAの方針で日本に1年間帰国しなければなりませんでした。その間も仕事はリモートで行っていましたが、オンラインでの会議などはやはり限界があるなと感じました。
NCGMは学びの機会が多い職場
――NCGMに入局されたのは2024年9月ですね。なぜNCGMに入りたいと思ったのでしょう。
金森 コンサルタント会社で技術協力の仕事をする中で、NCGMの国際協力局の方と知り合い、いろいろと話を伺ううちにNCGMに興味を持つようになりました。前職もやりがいのある仕事ではありましたが、NCGM国際協力局は国際保健の専門家の集まりであり、皆さん経験も知識も豊富で学びの機会が多いと聞きました。それが入局理由の一つです。
――現在、NCGMではどのような仕事をしていますか。
金森 今は「展開支援課」に所属しています。この部署は、日本の医療技術と製品を途上国へ普及するのが主な業務で、例えば内視鏡などのように途上国で必要とされているものを輸出しつつ、技術的に不足している部分の研修もパッケージで提供するようなことをしています。
その中で私は、途上国でさまざまな疾患を診断するために必須とされている対外診断薬や診断方法のリストを作り、ASEAN各国に普及させるという仕事をしています。疾患が適切に治療されるためには、それが正しく診断される必要があります。しかしながら途上国では、使われる診断薬や診断方法が適切でなかったり、科学的な根拠に基づいていなかったりする場合があり、患者が適切な診断を受けることができない場合が多いのです。そのような状況を改善するために、国として必須とされる体外診断薬・方法のリストを作成し、医療現場に導入することで診断を標準化し、質を高めることを進めています。
まだ入局したばかりでもあり、今はこの仕事を一生懸命やっていきたいと思っていますが、いずれは研究活動も行いたいと考えています。
――最後に、国際保健に興味を持っている読者にメッセージをお願いします。
金森 いろいろなプロジェクトに参加すると、異なる専門分野に対応しなければならないことが多くあります。学び続けるということはどんな仕事でも同じかもしれませんが、国際保健の分野は特に、新しいことに挑戦する度合いが高いと思います。ですから、常に学び続けることが好きな人、楽しいと思える人には向いている仕事なのではないでしょうか。
私が国際保健の博士を取得したのは、47歳の時です。そんな年齢になっても勉強しているというのは、国際保健に携わる人の特徴かなと思います。