2025
04/04
国際保健外交スキルが必要な時代になっている
-
国際医療
-
海外
~グローバルヘルス政策のための研究・人材育成の仕事~
海外で活躍する医療者たち(44)
社会や家庭の問題が子どもに投影されてしまう
――まず、小児科医になった理由を聞かせてください。
細澤 小学生時代にアメリカで過ごしたことがあり、将来は国際貢献に関わる仕事に就きたいと漠然と思っていました。その後、中学生の時に病気をして入退院を繰り返した時期がありました。主治医の先生をはじめ、病院の方々にとてもお世話になったことがきっかけで、お医者さんという仕事もいいなと思うようになりました。私は子どもが好きだったので、医師になるなら子どものお医者さんになりたいと思っていました。
――小児科の中でも、児童精神科に進んだのはなぜですか。
細澤 小児科医になったばかりの頃に担当した2歳の患者さんが、急性脳症の方でした。一命は取り留めましたが、意思の疎通が難しい状況でした。でも発達検査の様子などを見ていると、発語はなくても分かっていることがあることが分かりました。身体的な病気を治療することも大事ですが、子どもの発達やメンタルヘルスをサポートして、より良く生きていけるようにすることも大切だと感じ、児童精神科の領域を選びました。
児童精神科の臨床をしていると、発達障がいの人、思春期の気持ちの落ち込みや不登校の人も診察に来ます。しばらく診療をしていると、その子どもの精神的問題の背景には家族が抱えている問題や社会的な問題がある。そういった問題が一番弱い立場の子どもに投影されている場合があることに気が付きました。子どもが育つ環境を改善すれば、心の問題で受診する人も減るのではないかと思うようになりました。医師13年目にして公衆衛生を学び、また2018年から2年間、イギリスの大学でライフコース疫学の研究をしました。

近所の公園から望むロンドン市街。休日はよくここで過ごしていました。
――発達障がいも含め、子どもの精神科領域のことに対する見方や反応は、この10年ぐらいの間に変わったように思います。
細澤 そうですね。2005年に発達障害者支援法が施行されてから、徐々に社会にも浸透していきました。最近ではコロナ禍を経験したことで、子どもがメンタルヘルスの問題を抱えることがあることも広く認識されるようになったと思います。
また10年ぐらい前には、患者さんの保護者から「(発達障がいの)診断を付けないでほしい」と言われることもしばしばありましたが、最近では、学校などでのサポートも受けられるのではっきりわかった方がいいという方が増えています。私が行った研究でも、発達障がいの診断が早い年齢で付いた人ほど、思春期の抑うつなどの二次的問題が起こりにくいという結果でした。おそらく、診断が付くことで適切な治療や、周りの方々の理解やサポートが得られ、その中で成長してきたことが影響しているのではないかと思います。
――子どもの精神科領域の疾患と社会的背景の関係について、エビデンスに基づいて明らかにしていく研究をしてきたのですね。
細澤 そうですね。医学としては生物学的な側面から治療法を見つけていくことはすごく大事なことだと思います。一方で、病気の要因には遺伝的、生物学的なものだけはなく、その人が生活してきた社会環境からの影響もあります。ですから、個人の生物学的な要因に的確に対処するというアプローチも、集団として社会環境の改善方法を考えるというアプローチも、両方が医学には必要なのだと考えています。
国際保健の場は、多様化、複雑化している
――NCGMへの入局は、2020年ですね。
細澤 はい。日本に帰国した後は臨床に戻るか、疫学研究を続けるかと考えている時に、NCGMのグローバルヘルス政策研究センター(Institute for Global Health Policy Research、以下iGHP)のお話をいただきました。疫学も含めていろいろな研究をしている機関ですし、子どもの頃、国際貢献をしたいと考えていたこともあり、入局を決めました。
――現在先生が所属しておられるiGHPでは、どのような取り組みをしているのでしょうか。
細澤 iGHPは、グローバルヘルス政策を進めるための科学的エビデンスの構築と国内外への発信、政策提言、そのための人材育成をミッションに活動しています。グローバルヘルスに関する3つの研究科(システム・イノベーション研究科、外交・ガバナンス研究科、指標・評価研究科)で構成されており、互いに連携したり協力したりしながら、いろいろなプロジェクトを進めています。
――細澤先生は、どのようなプロジェクトに携わっておられるのですか。
細澤 私は主に、国際保健外交人材の育成、新型コロナウイルス感染症(コロナ)関連の政策研究、子どものメンタルヘルスの国際比較研究に携わっています。
国際保健外交人材の育成では、国際保健外交の現場経験がある先生を講師に、国としての考えのまとめ方や伝え方、相手をどのように理解し交渉すればよいかなど、ワークショップを開催したり、テキストを作成したりしています。研究の一環として研究班から世界保健総会にも参加しています。
現在は若手・中堅の実務家の方を対象にしていますが、今後は取り組みの範囲を広げたいと考えています。一つはアドバンストコースのような位置付けで、会議での意見集約、合意形成をリードしていけるようなチェアパーソン育成のプログラムです。もう一つは逆にビギナー寄りで、主に学生さんなどを対象とするものです。関係する大学機関などとも連携しながら、国際保健外交を知り、興味を持ってもらえるような取り組みを準備しているところです。
――なぜ今、国際保健外交人材の育成が必要なのでしょうか。
細澤 現在、国際保健の場は“国対国”で仕事をするだけでなく、多様化、複雑化しています。複数の国、民間企業、NGOなど関係者が増え、意見集約が難しくなっています。複雑さに耐えながら、相手や相手の背景を理解し、エビデンスに基づき課題の解決や合意形成を図れる人材が必要になっています。同じような問題意識を持つ国も多く、国際保健外交人材の育成は世界的な流れになっており、教育プログラムを持っている各国とのネットワークもあります。iGHPもそこに参加して、必要な人材についてディスカッションをしたり、各国と一緒にプログラムを作ったりしています。
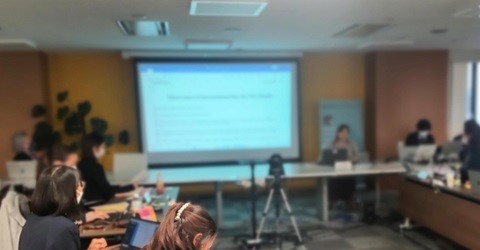
iGHPでは模擬世界保健総会を行い、国際会議で活躍する人材の育成を行っています。
子どもの“孤独感”の背景には何があるのか
――コロナ関連の政策研究についても教えてください。これはどのような研究なのでしょう。
細澤 いろいろな機関と協力して、コロナの罹患後症状に関する疫学研究を行っています。具体的には、コロナで入院した人に関する退院後の健康状態の調査、地域の中で感染した人と感染していない人の長期的な観察などを行い、毎年報告書にまとめています。私は子どもを中心に担当していて、子どもの罹患後症状がどのくらい続くのか、学校や日常生活にどういう影響があるかなどを研究しています。
この研究の一番の目的は、実態を明らかにすることで必要なサポートを考えるための資料にしていただくことですが、今後のパンデミックに備えてコロナの影響を記録として残すという意味でも大事な研究だと思っています。
――では、子どものメンタルヘルスの国際比較研究とはどのような研究なのでしょう。
細澤 イギリス滞在中に携わった研究がきっかけになっています。元々イギリスのデータを使って子どものメンタルヘルスの研究をしていましたが、ある時、これは日本の子どもたちにも当てはまるのだろうか、と疑問に思いました。そこで、日本とイギリスの両方が含まれているデータセットを使って両国を比べることによって、共通点や相違点が見えてくるかもしれないと思って始めました。
データセットは、WHO、OECD、ユニセフなどの国際機関が収集して一般公開しています。そういうデータを使いながら、国ごとの違いや、その国の中のジェンダー格差や経済格差による違いなどを見ています。

毎年5月にジュネーブで開催される世界保健総会にも参加し、発言を行いました。
――今はどのようなテーマで研究しているのですか。
細澤 最近は、“子どもの孤独感”が世界の国々でどのように違うのかを研究しています。今取り扱っているのは70カ国程度ですが、その中でもいろいろなことが分かります。
例えば子どもが孤独感を感じる頻度は国によっても異なります。この20年間では、2010年代からは急激に子どもの孤独感が高まっており、特に高所得国の女子の孤独感が顕著に増えています。低中所得国でも、高所得国ほどではないですが、女子の孤独感が高まっている状況があります。
――2010年頃、あるいはそれ以降の何が原因なのでしょうか。
細澤 スマートフォンやSNSが普及したのがちょうどそのくらいの時期で、テクノロジーの進化と関係があるとも考えられます。他にも、核家族化や都市化、格差拡大など社会構造の変化との関連も考えられます。何が原因かについては、もっと多くのエビデンスを積み上げていく必要があると思っています。研究者の「きっとこうだろう」という考えは、違うこともあるといわれていますので、やはり当事者の声を聞きながら、研究を進めていくことも必要だと思います。
――では最後に、読者にメッセージをお願いします。
細澤 目的地が明確にあって、そこに向かって進んでいくというキャリアの築き方もありますが、私の場合は目の前のことに取り組んできた結果、振り返ってみると一つの道につながってきたように思います。時々、全然違うことをやっているような気がして不安になることもありましたが、経験に無駄はありません。その時関心を持ったこと、求められたことを一生懸命やっていく中で、道が開けていくというキャリアの積み上げ方もあると思います。
国立国際医療研究センター(NCGM)は2025年4月1日、国立感染症研究所との統合により、国立健康危機管理研究機構 (JIHS)に生まれ変わりました。


